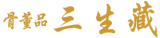中国仏像について
中国仏像のはじめ
考古学的に中国へ仏教が伝来したのは西暦67年の『白馬寺の求法説』に中国から派遣した使者及びインドの高僧たちが、白馬寺に経典と仏像を運んだ、とされています。最古の仏像とされています。白馬寺は中国に仏教が伝来して最初に国費で創建された寺院です。(白馬寺に伝わったとされる仏像は今では現存していません)サンフラシスコのドゥ・ヤング記念博物館の建武四年像(西暦338年作)である金銅物座像には制作年がはっきりと刻まれ、それを証拠に中国最古の仏像とされています。
歴史Ⅰ
仏教はシルクロードを通って中国地域へ伝わり、南北朝時代(439~985年)、国家の保護のもとで仏教は急速に繁栄していき、5世紀には900近くの寺院が建立されて、多くの仏像が造られました。
北周(557~581年)の武帝による廃仏(仏教弾圧の項をご覧ください)から、特に中国の北方では無宗教政治が続き、その後、隋(581~619年)が建国され初代皇帝の文帝が即位すると、直ちにに詔を出し文帝自らが先頭に立って復興事業を進めていきました。
長安に新しく都城を建設し、城内に国立寺院の大興寺を建造させ、隋と次の王朝である唐(618~907年)の名立たる僧たちが住する中央仏教随一の名刹となります。そして国内の州県に州・県立の寺を建てるように勧めました。文帝は学徳の高い高僧を招くと、学僧たちに南北朝時代までの教学を学ばせました。
唐時代645年に玄奘三蔵が17年ものインドへの旅から帰国し、多数の仏像や経巻を持ち帰りました。皇帝の太宗は玄奘から西域地方に対する最新の知識を聞き、大いに喜んで当時の仏教界の俊英を集め、経典の翻訳を助けました。次の高宗の時代になると、玄奘が持ち帰った仏像や経巻が焼失するのを防ぐ為に、大雁塔を作らせました。
歴史Ⅱ 弾圧の歴史(寺院や仏像の破壊、財産の没収、僧侶の還俗)
三武一宗の法難(三武一宗の廃仏)
四人の皇帝が行った、中国史上最も規模も多きい廃仏事件。各皇帝の廟号や諡号を取って、こう呼ばれています。
北魏(386~534年)の太武帝の太平真君年間
北周(556~581年)の武帝の建徳年間
唐の(618~907年)の武宗の会昌年間
後周(951~960年)の世宗の顕徳年間
経済政策については二つほど理由があります。第一に国家公認の僧籍にある者は、納税の必要がありません。それを悪用し、脱税目的で僧籍を取った者を還俗させて課税者にする財政改善を狙った事。
第二に仏寺中の仏像や梵鐘資材を得る事です。銅(貨幣の材料)や鉄(武器の材料)を中心とした金属物資は、主に唐の武宗期の銅銭不足や、後周の世宗期による国家の再統一事業が絡む為に、重要な問題でした。廃仏は儒教や道教の中国古来の宗教を保護する為と考えられますが、経済政策の側面も持っていたと推測されます。